はじめに
マイケル・サンデルといえば「ハーバード白熱教室」と銘打ったハーバードでの授業や、東大の安田講堂で繰り広げられた対話型の授業を行なった先生としてよく知られている。加えて、『これからの「正義」の話をしよう』のなどのベストセラーも出版している。最近では『実力も運のうち 能力主義は正義か?』を出版したことで、再び注目が集まっている。
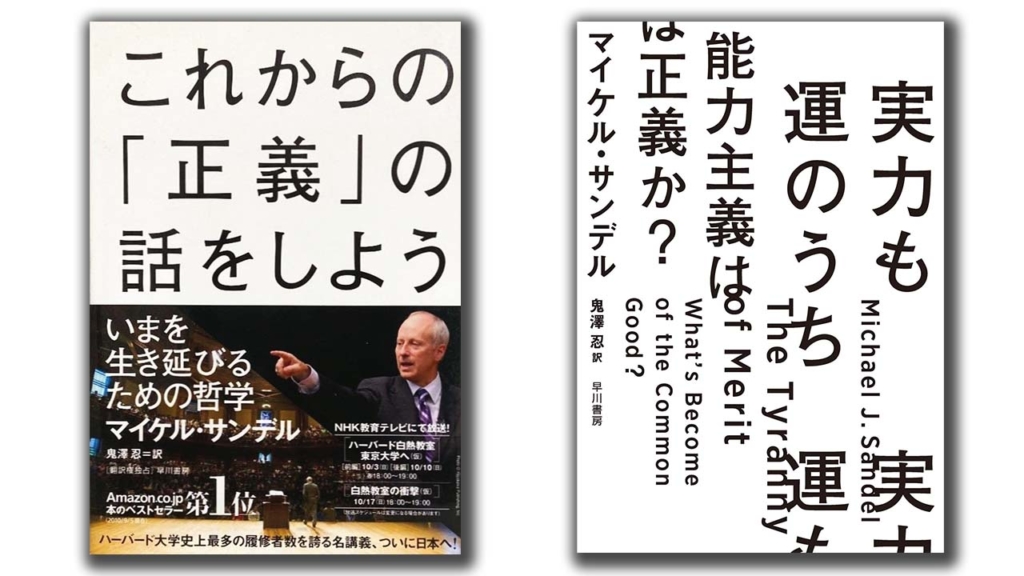
しかしながら、これらの著作や講義の知名度に比較して、サンデル自身の政治哲学について言及されることはあまりない。サンデルはアメリカの政治哲学者としても知名度が高く、コミュニタリアニズムの代表的な論者でもあるが、上記の著作や講義ではその側面についてはあまり言及されていない。そこで本稿は、サンデルの政治哲学における主著のうちの一つである『民主政の不満』を通じて、サンデル自身の政治哲学に焦点を当てる。その後、『民主政の不満』を含むサンデルのコミュニタリアニズム批判を行なった、日本の代表的なリバタリアニズム研究者である森村進の論考について言及する。
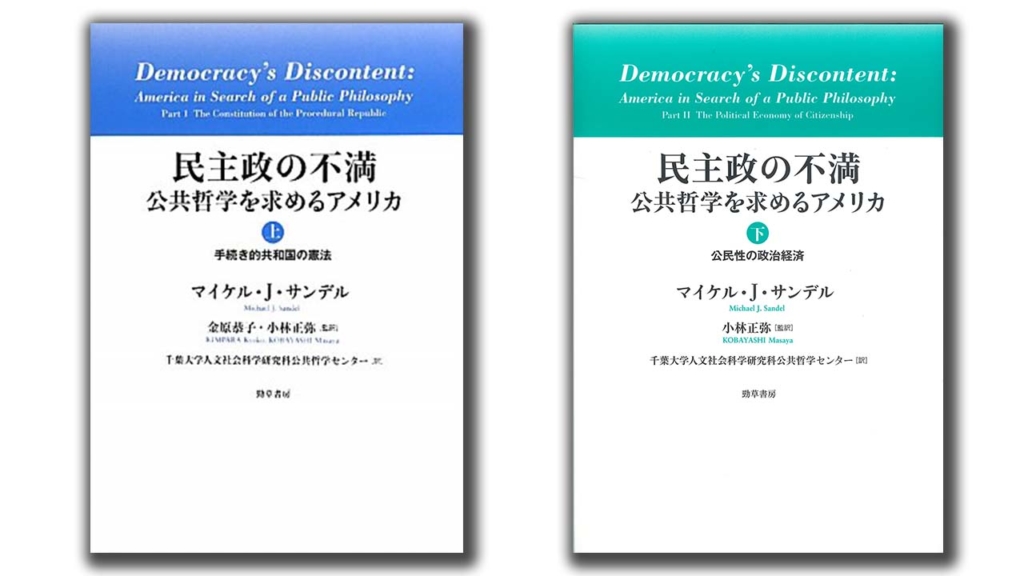
「正」と「善」からみたリベラリズム批判
コミュニタリアニズムを端的に述べるならば、公共空間における倫理性・道徳性(「善」)と、それらを育むコミュニティを重視する考え方である。
自由主義社会においては、個人がどのように生きるかについては個々人に委ねるという考え方が主流となっている。何をもって「善き生」とするかは人それぞれであるため、政府や国家は「善」について介入せず、「善」に対して中立的な立場から、正義や権利といった「正」について議論すべきだ、という考え方は、リベラリズムやリバタリアニズムの中である程度共有されている。(これは「善に対する正の優越」the priority of the right over the goodという標語としても知られている)
一方で、サンデルは上記の考え方に対し、「道徳的基礎がどこにあるのか」と批判を投げかける。リベラリズムの善に対する中立性においては、功利主義的な説明(一般的な福祉の最大化)と、カント主義的な説明(功利は道徳の基礎に合わないため、「正」と「善」を区別し、「正」を重視する)、最小限主義的リベラリズムの説明(ロールズらによる、政治と道徳の分離擁護)の3パターンがある。
功利主義とその批判に関しては別記事で詳細を解説したため、そちらを参考にしてほしい。
カント主義的な説明に対する批判
カント主義的な説明によれば、個人的権利は一般的な善より優先され、正義の諸原理は特定の味方に依拠しないことで、個人の権利の至高性を強調する。個人はそれぞれ個別的である、という考え方は、先行する道徳的な規範(自然や神、国家や文化、伝統など)と対立する。そして、カント主義的な考え方では、これらの道徳的な規範に基づく責務は説明できないため、「市民は何の政治的責務も負わない」という結論に行き着く。その結果、市民に期待される責任について説明できない、とサンデルは批判する。福祉国家において徴税と再分配はよく行われている訳だが、これらは「個人は個別的であり、他者の目的のための手段として利用してはならない」というカント主義的な説明と矛盾するのではないか、という批判に対して脆いわけである。(これはリバタリアニズムの福祉国家リベラリズムに対する批判にも通ずる)
人格に対する平等的な尊重のためには、社会的・経済的権利が要求されるという平等主義者に対しても、「共同体を想定しないのにもかかわらず、同国人に対して責任を持たなければならないのか」という疑問は残ったままである。カント主義的な説明では、道徳的な規範がないため、相互扶助を擁護できないとサンデルは批判する。
最小限主義的リベラリズムに対する批判
サンデルによれば、最小限主義的リベラリズムとは、自分達と無関係な道徳的・宗教的責務についてしばしば負うことを受け入れつつも、個人的な性格と市民的な性格を分離して考えるべき、という考え方であり、ロールズやリチャード・ローティなどに見出される。人間と市民のアイデンティティを分けて考えることで、善についての共通的な合意が得られない問題を回避する。そして、社会的協力による相互扶助によって多元的な道徳的・宗教的理想を尊重できるとして擁護する。
しかし、最小限主義的リベラリズムに対して、サンデルは道徳的・宗教的教義による利益を破棄するほどに、社会的協力や相互尊重の利益は圧倒的なのか?という問いを提出する。また、道徳的・宗教的に深刻な問題(サンデルが例に挙げたのは中絶と奴隷制)に関しては、政治的な解決のためには完全な分離は不可能であると指摘する。奴隷制に対する対立では、ある特定の道徳的理想(例えば奴隷制擁護)を非難することに至るが、これは最小限主義的リベラリズムの主張である、政治と道徳の分離と矛盾することを指摘する。
つまり、ロールズのリベラリズムの問題点として、政治と道徳の分離を前提としようとしても、一定レベル以上の社会的問題を判断するにあたっては何らかの道徳的基準を参照する必要があるため、そもそも政治と道徳の分離は困難であると指摘する。それなら、最初から公共空間における道徳について考慮した政治哲学が必要であり、それがサンデルのいうコミュニタリアニズム的共和主義なのである。
コミュニタリアニズム的共和主義
それでは、サンデルが述べるコミュニタリアニズム的共和主義とはどのような思想なのか。
ここでの共和主義について端的に述べるならば、「人々が政治に参加し、自治を行うことを公民的美徳とし、その公民的美徳を追求する」という立場である。そしてコミュニタリアニズムは端的に言えば、「善」とコミュニティを重視する立場である。ここから、コミュニタリアニズム的共和主義を一言で言い現わすと、「公共空間において「善」を重視し、かつ人々の政治参加も公民的美徳として重視する」と言えよう。

『民主制の不満』ではアメリカの歴史を振り返ったうえで、伝統的に見ると自由主義はここ4,50年のイデオロギーに過ぎず、初期のアメリカ合衆国においては共和主義が趨勢を占めていたことを指摘し、現在のアメリカを支配する政治的無力感と不平等による分断を脱却するためには共和主義の立場を再考することが望ましいとサンデルは主張する。
トクヴィル的な多元的共和主義
サンデルは共和主義における「排他的」「強制的」という批判も理解していた。古代ギリシアにおける共和主義の政治理論によれば、公民権を持つものとして、女性や奴隷、外国人は適さないとされている。サンデルは、時代が経るにつれて、「美徳は生まれながらにして備わっている」という考え方が減ってきた結果、「排他的」な側面は減退したと考える。一方で共同体の規模が拡大した結果、ポリスのような規模で考えることができなくなったため、自治を行うにふさわしい共通善の共有が難しくなったのだ。共同体が拡大し、構成員の違いが拡大すればするほど、共和主義が追求する美徳は押しつけがましいものになってしまう。
この問題に対し、サンデルはトクヴィル的な多元的共和主義で解決を試みる。ルソー的な人格間の距離を減らし、統一的な共通善を追い求めるのではなく、人格の差異を嫌わず、闘争的に共通善を競わせ、民主主義的で多元的な形で、複数の共通善を保持しようという試みである。
サンデルはコスモポリタンに対して批判的である。 普遍的な共同体ではサンデルが重視する自己統治の公共哲学に適さないからである。 普遍的な概念を特定的な概念より重視する考え方はカント以来さまざまな知識人によって試みられてきたが、いずれも非現実的であるという批判からは免れにくい。「普遍的な人類愛」よりも「家族や恋人、夫婦の愛」の方がイメージしやすい例は、共同体においても当てはまる。かつては国民国家が一つの共同体としてアイデンティティと自治のつながりを提供していたが、グローバル化が進む現代社会においてはそれも難しい。それならば、共同体や政治体を複数重なり合わせて主権を分散させ、人々の政治的な参加を促し、狭い地域での自己統治の実践からより広い領域の政治活動を促進させられるとサンデルは考える。
リバタリアンから見たサンデル批判
サンデルの『民主制の不満』について見た後は、この書籍に対する反論を、森村(2020)に依拠しつつ見ていく。
公共善および自己統治の過大評価
サンデルが展開するコミュニタリアニズム的共和主義では、政治参加による自己統治(共和主義)と、ローカルコミュニティにおける公共善(コミュニタリアニズム)が重要視されているが、この二つが過大評価されていると森村は批判し、私も同意する。
公共善や自己統治に対して一定の価値は存在しうるし、それらを追求する人々や共同体自体は否定しないが、これらを政治的に行わなければならない課題とするのは疑問である。
人々が誰しも公共善や自己統治に関心があるわけではない。政治参加による自己統治を万民が望んでいるわけではない。そのような状況下で公共哲学として道徳や公共善を公共の課題として追求すること自体、それぞれの道徳に対する干渉と言わざるを得ない。端的に言ってしまえば「余計なお世話」なのである。
森村は「我々は人々が求める「善」の中には公共善だけでなく、個々人の間で異質なもの、それどころかしばしば衝突するものがあるという現実を直視しなければならない。社会道徳は何よりもまず、その事実から生ずる人々の間の対立と衝突を解決して社会に平和と繁栄をもたらすための手段であるべきだ」(p.76)と述べる。社会道徳の目的に「繁栄」を志向する必要があるかは個人的には疑問だが、個々人や組織の衝突を解決するための手段として道徳や法といった規範がある。衝突を解決する以上の役割を規範に求めてしまうと、そこからもたらされる弊害の方が大きくなる。
「連帯感」は公が担う問題ではない
サンデルは、リベラリズムに対し道徳的・政治的な責務を説明することができないとして批判するが、はたして本当にそうだろうか。
ノージックのような最小国家論者であっても、司法や安全保障のために国家の存在が必要だと述べ、そのための徴税を認めている。税金を支払うことはある程度の政治的責務を果たしている。それ以上の責務や連帯感は個々人や所属する組織の必要性に応じて考えるべき問題であり、一律に押し付けるべきものではない。道徳的責務に対しても、いかにリベラルといえども一切の道徳を持っていないわけではないだろう。私たちはたとえ法律の制限がなくとも、むやみに動物を殺めたりはしないだろう。そしてこれ以上の道徳的責務を普遍的に共有しなければならない必然性もまた見当たらない。
多元的な共同体を基礎づける公共哲学としてふさわしくない
サンデルはトクヴィル的な共和主義を念頭に、主権の分散や複数の重なり合う共同体の構築といった主張を行う。このうち、主権の分散や複数の共同体に関してはリバタリアニズムが主張するところと重なり合う部分がある。しかし、さまざまな共同体を基礎づける政治哲学としてコミュニタリアニズム的共和主義が適切だとは思えない。その理由は簡単で、共和主義を根本の公共哲学として持ってしまうと、共同体に対して認められる自由度が減少するからだ。
例えば、「一定税率を払えばそれ以外制限なし。政治参加も不要」という共同体Aと、「自分とみんなのために政治参加しよう」という共同体Bを考え、それぞれの移動は自由だと仮定する。リバタリアニズムが公共哲学として存在する場合、AとBはどちらも成立しうる。一方サンデルの共和主義が公共哲学として存在する場合、Aが認められるかは疑問である。
多元的な共同体が成立するためには、それらを基礎づける公共哲学はできる限り最小限であることが望ましい。法律を考えてみればわかりやすいが、憲法が厳しい場合、その上に成立する個々の法律はもっと厳しくなる。これらを踏まえたうえで、サンデルの共和主義はさまざまな共同体が成立するためには厳しすぎる。
サンデルが批判するリベラリズムの中身
サンデルが提出するリベラリズム批判は、基本的にロールズが念頭に挙がっていることを森村は指摘する。コミュニタリアニズムは「正」と「善」を区別しない。さらにリベラリズムも、代表的な論者であるロールズやドヴォーキンは暗黙の裡に「善き生」が想定されている。(森村によればロールズ『正義論』第3部やドヴォーキン『平等とは何か』第6章、『ハリネズミのための正義』第3部など)一方、公共哲学において「正」と「善」をより区別しているのはリバタリアニズムであり、それらを分ける境界線として自己所有権や消極的自由が挙げられる。
正義論における中立性について考慮するとき、ロールズやドヴォーキンのような平等主義的リベラリズムよりも、ノージックや古典的自由主義者のリバタリアニズムの方がよりコミットしている。なぜなら、格差原理といった分配的正義においては、リバタリアニズムと比較して道徳的に恣意的にならざるを得ないからである。(ただし、恣意的なこと自体が問題ではなく、結果として権利を侵害することや、結果として優れていないことが問題なのである)
「正」と「善」の区別に対して「深刻な問題の場合暗黙の裡に道徳にコミットしている」と批判するならば、その批判先はリベラリズムではなくリバタリアニズムが適切であろう。
公共空間における道徳の扱い
ここまで、サンデルの主張とそれに対する反論を概観してきた。最後に、筆者におけるコミュニタリアニズムに対する現時点での評価を述べる。
コミュニアリアニズムの主張自体はある程度同意せざるを得ない部分も多い。特に善に対する扱い方としては、中立性を標榜しつつも暗黙の裡に一定の立場の善にコミットメントしているリベラリズムよりも、正面から道徳を理論に組み込もうとするコミュニタリアニズムの方がより正面から問題を向き合っていると言えよう。
しかしながら、コミュニティの公共善を考察するうえで、コミュニティのサイズは外せないポイントになってくる。そして、ある程度のサイズを超えてくる場合、コミュニタリアニズムを成立させることは容易ではない。市町村未満の自治会や、会社組織・宗教組織といった特定の目的にコミットメントしている組織では、コミュニタリアニズム的な考え方がなじむであろうが、市町村を超えてくるサイズの自治体における公共哲学としてはふさわしいとは思えない。
参考文献
サンデル M. (2010). 民主政の不満: 公共哲学を求めるアメリカ (金原 恭子小林 正弥, trans.). 勁草書房.
キムリッカ W. (2005). 新版 現代政治理論 (千葉眞 & 岡崎晴輝, trans.). 日本経済評論社.
森村進. (2020). 法哲学はこんなに面白い. 信山社.
サンデル写真 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Michael_Sandel_Me_Judice.png






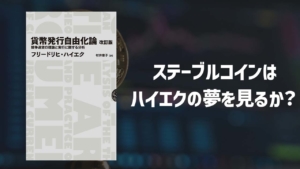
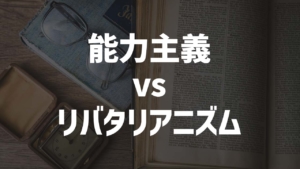

コメント